






| HOME>遺産相続手続き(遺産相続の仕組み・流れ 遺言の必要性・種類) | ||||||||||||||||
| 遺産相続手続き | ||||||||||||||||
| 遺言の文書 | ||||||||||||||||
| 遺言は自分の財産を自分の意思で自由に処分することができることをその死後にまで認めた法律上の制度です。 遺言は自分の財産を築くことに多大に貢献したり、肉親以上に尽くしてくれた人達に対し、法律と異なった割合で、財産を譲り、または、死後贈ることができます。(法定相続分の修正)また、事業を承継するものには、事業が円滑に継続されるよう、分割方法の指定等をすることができます。(事業用財産の承継)また、相続人間に配慮した公平な分割方法は、遺産分割をめぐる紛争の予防にもなります。(紛争の事前予防)法律に従った要式であれば、死後、不動産の登記や預金の引き出し等もスムースにすすみます。(相続手続きの円滑化) |
||||||||||||||||
| 遺産相続の仕組み | ||||||||||||||||
| ①相続は遺言があれば遺言が優先する。 但し遺留分減殺請求制度がある ②遺言がない場合には法律(民法)で法定相続分が決まっている。
|
||||||||||||||||
| 遺産相続の流れ | ||||||||||||||||
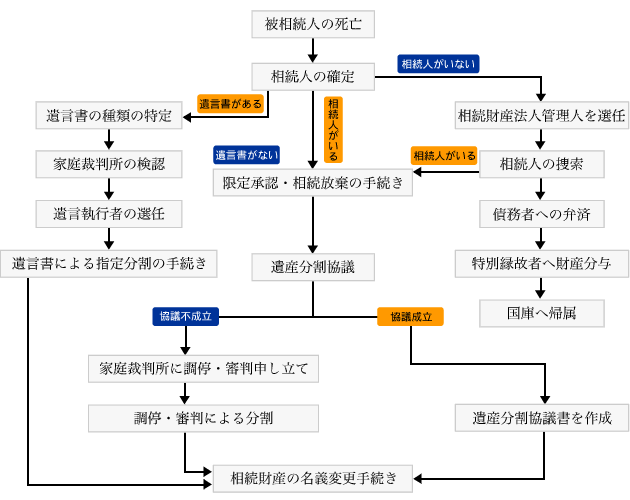 |
||||||||||||||||
| 遺言書の必要性 | ||||||||||||||||
| 遺言書が必要なのは富裕層だけではない。親族間の争いを避け将来に禍根を残さないためにも多少なりとも以下の事情がる場合には遺言書を用意するなど対策をとることが望ましい。 | ||||||||||||||||
| ・2人以上の子供がいる ・不動産などの分割しにくいものが財産の大半を占める。 ・親と同居している子供と別居している子供がいる。 ・結婚を数回しており、親の異なる複数の子供がいる。 ・会社を経営している。 ・家族以外に死後財産を譲りたい。 |
||||||||||||||||
| 遺言書の種類 | ||||||||||||||||
| 遺言には普通方式遺言と特別の事情の場合の特別方式遺言があるが通常は普通方式遺言で行われる。 1. 普通方式遺言 |
||||||||||||||||
| ①自筆証書遺言の場合 〈方 法〉 自筆証書遺言は遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自署し、これに押印する遺言方法です。 〈メリット〉 ・最も簡単に作れる。 ・費用がかからない。 ・証人、立会人がいらないため、秘密性が保てる。 〈デメリット〉 ・保管が難しく、発見できないままになる可能性がある。 ・形式面、内容面の誤りによって、その効力が問題となる。 ・遺言書の検認(家庭裁判所による)手続きが必要となる。 ② 公正証書遺言の場合 〈方法〉 公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもとに、公証人が遺言者の口述を筆記して遺言を作成します。 〈メリット〉 ・遺言の保管の安全性が保たれ、紛失・改変のおそれがない。 ・公証人が関わることで、遺言の形式・内容、遺言能力等の有無についてのトラブルが回避できる。 ・遺言書の検認(家庭裁判所による)手続きが不要である。 〈デメリット〉 ・手続きが煩雑。 ・作成費用がかかる。 ・証人2人が必要で、秘密性が万全ではない。 ③ 秘密証書遺言の場合 〈方法〉 秘密証書遺言は、遺言者が遺言書(代筆、ワープロ、タイプライターで作成可)に署名・押印して封筒にいれ、同じ印で封印し、公証人、証人2人以上の前で自分の遺言書であること申し述べ、公証人が証人とともに署名、押印する方法です。 〈メリット〉 ・秘密性が保てる。 ・費用が公正証書遺言より安価である。 ・公証人の関与により、偽造・変造のおそれが少ない 〈デメリット〉 ・遺言書の保管場所の確保が困難。 ・遺言の内容面の不明確さが残る。 ・遺言の検認(家庭裁判所による)手続きが必要である。 |
||||||||||||||||
| 標準となる料金 | ||||||||||||||||
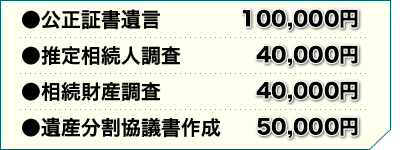 詳細はぜひご相談ください。 |
||||||||||||||||
Copyright2009. 久野行政書士事務所 All right reserved.
〒306-0126 茨城県古河市諸川1709-6
TEL 0280-76-4767 FAX 0280-76-4769
〒306-0126 茨城県古河市諸川1709-6
TEL 0280-76-4767 FAX 0280-76-4769