






| HOME>法人設立手続き(会社設立 社団法人設立 医療法人設立 社会福祉法人設立) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人設立手続き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会社を設立するには | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式を設立するには以下のスケジュールにしたがって手続きが行われます。 (以下は発起設立のケースです。) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 会社設立についての方針打ち合わせ 2. 会社設立についての行政書士への委任 3. 定款の作成と手続きの流れ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇ | 標準となる料金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
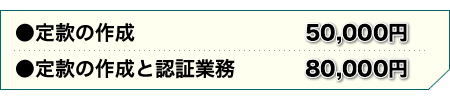 詳細はぜひご相談ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会社の清算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
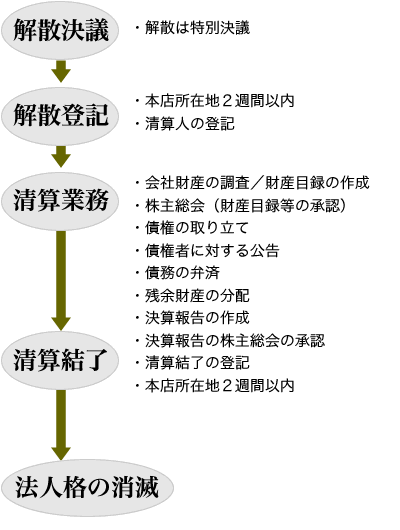 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇ | 標準となる料金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
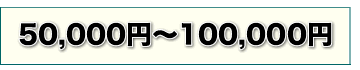 詳細はぜひご相談ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社団法人を設立するには | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
新・営利法人制度が平成20年12月1日からスタートしました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
例 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・まち興しなどの地域振興団体 ・同窓会や同業者団体など公益性を有する団体 ・学術団体、環境保護団体など公益性を有する団体 ・介護支援や生活・健康の増進など公益性を有する団体 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
特徴 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・官庁の許認可は必要ない ・事業に制限がない。収益事業を目的にすることができる。 ・社員2名から設立が可能 ・準則主義を取っている。(要件を満たせば登記を経て設立できる) ・剰余金の分配ができない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
設立手続の流れ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ①定款の作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・目的 ・名称 ・主たる事務所の所在地、 ・社員の名前 ・事業内容 ・会員資格の制限 ・総会の規定 ・役員の規定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ② 定款の認証 ③ 所定の資料作成 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・登記事項を記したFDを用意 ・印鑑届出書 ・定款 ・設立社員全員の同意又は一致があったことを証する書面 ・設立時理事の就任承諾書 ・設立時理事の印鑑証明書 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
④ 法務局に登記申請
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇ | 標準となる料金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
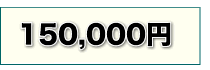 詳細はぜひご相談ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療法人を設立するには | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所または介護老人保健施設を開設しようとする社団又は財団は、この法律(医療法)により、これを法人とすることができる。(医療法39条1項) 前項の規定による法人は、医療法人と称する。(医療法39条2項) ※社団 通常複数の者が出資して設立。出資額に応じて出資持分を有する。出資持分は、退社、解散の折、持分に応じて払い戻しを受ける。 ※財団 個人又は法人が寄附した「財産」に基づき設立。持分は与えられません。解散した場合は理事会で処分方法を決め、知事の認可を受けて処分する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 医療法人は、都道府県知事の認可を受けなければこれを設立することができない。(医療法45条) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● |
医療法人を設立しようとするものは、定款または、寄附行為をもって、少なくとも次に掲げる事項を定めなければならない。(医療法44条)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療法人設立の流れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会福祉法人を設立するには | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
特別養護老人ホーム(第1種社会福祉事業)や保育所を経営する事業など(第2種社会福祉事業)の社会福祉施設の経営は、原則として社会福祉法人でなければ行うことはできません。したがって、施設整備に当たっては、施設の建設に先立って施設を経営する社会福祉法人の設立認可を受ける必要があります。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■主たる手続きの流れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■法人の資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 法人は、社会福祉事業を行うために直接必要なすべての物件について所有権を有していること、又は国若しくは地方公共団体から貸与若しくは使用許可を受けていること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 社会福祉施設を経営する法人にあっては、施設の用に供する不動産(=土地及び建物)は、原則として基本財産としなければならないこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) |
法人を設立する場合にあっては、必要な資産として、運用財産のうちに当該法人の年間事業費の12分の1以上に相当する現金、普通預金又は当座預金等を有していなければならないこと。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇ | 標準となる料金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
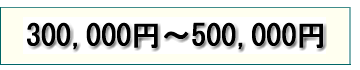 ※別途事業計画、資金計画、施設計画等の策定と事業推進のコンサルティングの包括的な取り組みも可能です。 詳細はぜひご相談ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒306-0126 茨城県古河市諸川1709-6
TEL 0280-76-4767 FAX 0280-76-4769