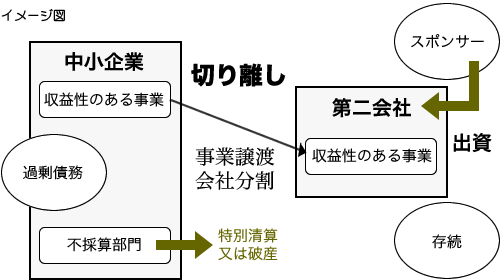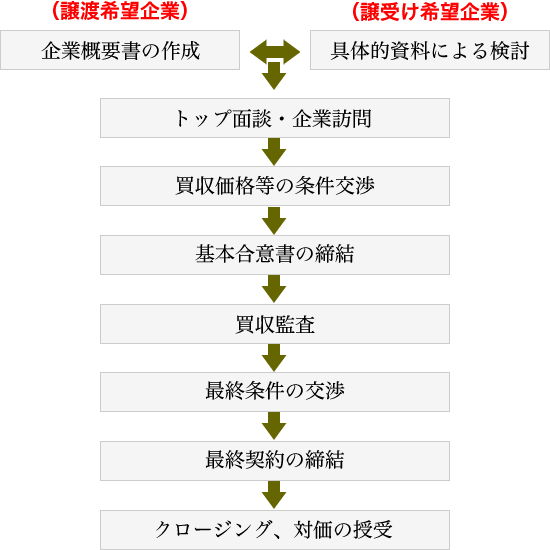| HOME>コンサルティング(中小企業継承事業再生計画 事業承継 画,経営革新 顧問契約サービス M&A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンサルティング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企業継承事業再生計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
平成21年6月22日に産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法が施行され、中小企業の事業再生の円滑化を目的とし、第二会社方式による「中小企業継承事業再生計画」の認定制度が創設されました。
※新設分割を用いる場合など、特定中小企業者自身が「承継事業者となる法人を設立しようとする者」なることも想定されています。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
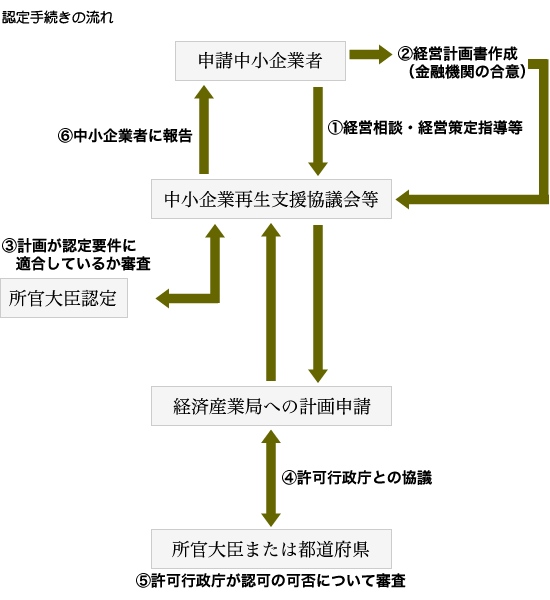 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業承継計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 我が国の99%以上が中小企業であって、雇用人数も70%以上を中小企業が支えているのが現状です。しかしながら、1986年に約533万社あった中小企業は2006年には約420万社に、20年で約113万社も減少しています。(2008年版中小企業白書) 経営者の多くは戦後の日本経済の復興に大きく携わり、正に日本を世界第2位に押し上げた功労者であります。その経営者達が高齢化するなかで、その事業を次世代にどのように円滑に承継するかが大きな課題になってきました。 しかしながら、約7割の中小企業の経営者は事業承継の準備をしていないか、或いは不十分であるとアンケートに答えております。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 社内・親族に後継者がいない 2. 経営が不安定で後継者を決めかねている 3. 後継者が未熟で継承に不安がある 4. 事業承継に際しての資金調達が心配だ 5. 相続紛争が心配だ 6. 相続税・贈与税が心配だ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企業経営承継円滑化法の定める中小企業社は中小企業基本法上の中小企業者を基本として、政令によって、ゴム製品製造業、ソフトウエア・情報処理、サービス業、旅館業についてその適用範囲を拡大しています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企業経営承継円滑化法における3つの制度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
① 相続税等の課税措置(非上場株式等に係る相続税等納税猶予制度) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一定の要件を満たした非上場中小企業株式に係る課税価格の80%に対応する相続税を納税猶予する制度を創設。 ※贈与税の納税猶予制度が平成21年度税制改正で導入が決まった。贈与税の納税猶予制度は事業を承継する後継者が、先代経営者から株式の贈与を受けた場合に、一定の要件を満たすことにより、当該株式(贈与前から既に保有していた議決権株式等を含めて、その会社の発行済議決権株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分に限る)について贈与税の全額が猶予される制度をいう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
②民法の特例 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生前贈与株式を遺留分減殺請求の対象外とする制度及び当該株式の評価額をあらかじめ固定する制度を創設。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
③金融支援(中小企業信用保険法等の特例) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経営者の死亡等に伴い必要となる資金の調達を支援するため、適用対象事業者及び後継者に対して、中小企業信用保険法等の特例を創設。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経済産業大臣の認定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贈与税や相続税の納税猶予を受けるためには、「経済産業大臣の認定」を受けておくことが前提となります。認定には贈与の実施や相続が開始する前の事前確認、贈与実施や相続開始後の認定、その後の5年間にわたる報告の3つの手続きからなっています。 つまり、贈与であれば贈与の前に計画的な承継に係る取組みについての確認を受けておいて、贈与が行われたら贈与税の申告期限までに認定を受け、その後5年間毎年1回、事業継続報告を提出します。 また、相続であれば、被相続人の生前に計画的な承継に係る取組みについての確認を受けておいて、被相続人が死亡して相続が開始したら相続税の申告期限までに認定を受け、その後5年間毎年1回、事業継続報告を提出します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業承継計画の取り組み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
① 事業承継計画の必要性 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業承継の方法や後継者が決まったら中・長期承継計画を具体的に定め確実に準備を進めることが重要です。つまり、計画を立てることで、経営者と後継者のやるべきことを整理・確認することができます。計画的に得意先や仕入れ先、金融機関などとの信頼関係を築く手順も見えてきます。さらに、後継者に計画的に社内業務に就かせ体験によって業務の理解や自覚や意識を高めることができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
② 事業承継計画の策定手順 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
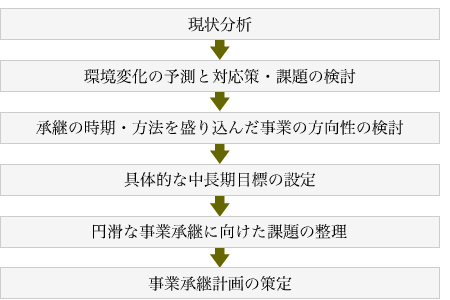 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経営革新計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今、「100年に一度の大不況」と形容される世界同時不況を経て、わが国も僅かながらいくつかの経済指標に回復がみられますが、依然として雇用の悪化と設備投資の減退について歯止めがかかっておりません。未だに緊迫した状況を脱出したとはいえる状況ではありません。 多くの中小企業は売上の低迷と資金繰りの悪化の差中にあるといえます。 しかしながら、このような状況を手をこまねいて見ているわけにはまいりません。企業は社会的使命からその継続性を求められております。 この、厳しい環境下であっても生き残りを賭けて経営を続けることを経営者に期待されております。 企業は生き物です。多くの生物が環境の変化に耐え、生き残るように企業も環境に合わせて変化しなければなりません。 今こそ、環境変化に適合した新しい経営計画が要求されております。それが経営革新計画なのです。 「経営革新」は事業者が新事業活動に取り組み、経営目標を設定し、経営の相当程度の向上をはかることです。(中小企業新事業活動促進法) この「経営革新」には次のような特徴があります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ① | 特に業種による制約条件をつけない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ② | 単独の企業だけでなく、任意のグループや組合などの柔軟な連携体制での経営革新計画の実施が可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ③ | 具体的な数値目標を含んだ経営革新計画の作成が要件となっている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ④ | 都道府県等が、承認に対して、経営革新計画の開始から1年目以降2年目以前に、進捗状況の調査(フォローアップ調査)を行うとともに、必要な指導・助言をおこなう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新事業活動の例を上げると | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 観光旅館が、空き部屋を日帰り客向けのリラクゼーションルームとして改装し、新しいサービスを行う。それにより昼間の時間帯の増収を図るとともに、そこから新規宿泊客の拡大に結び付ける。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 日本酒の売上が減少傾向にある蔵元が、道路に面した酒造工場を一部店舗に改装して、試飲コーナーとお土産コーナーを設置した。観光バス会社との提携でバスも立ち寄ることになり売りあげ増に結び付けた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経営革新計画が承認されると | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 税の特例措置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・設備投資減税 ・同族会社の留保金課税の停止措置 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 保証・融資の優遇措置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・信用保証の特例 ・政府系金融機関による低利融資制度 ・高度化融資制度 ・小規模企業設備資金貸付制度の特例 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 投資・補助金の支援措置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ベンチャーファンドからの投資 ・中小企業投資育成会社からの投資 ・経営革新関係補助金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 販路開拓の支援措置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・販路開拓コーディネーター事業 ・中小企業総合展 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | その他の優遇措置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・特許関係料金減免制度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※計画の承認は支援措置を保証するものではありません。 計画の承認後、利用を希望する支援策の実施機関の調査が必要になります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇ | 標準となる料金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
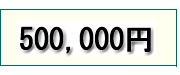 詳細はぜひお問い合わせください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧問契約サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経営・財務・法務等に関する総合的な助言・アドバイスサービスとして顧問契約方式をとります。 主として事業を営む事業者に関わる相談事項は単に許認可を得る、遺言を作成するといった手続き的な代行業務の性格から、許認可を得て事業を立ち上げ成功させるといった、上位の目的を有し、その実現のためにはその企業の経営資産である人、物、金、情報の効果的な活用が必要となります。したがって、常日頃から経営者や社員等と緊密に接触する機会を持つことが非常に大事になり、事業者の考え、人脈、社員の価値観、組織風土など固有の情報や状態を熟知し、それを反映した的確な実務的なアドバイスや取り組みで大きな企業価値を生みだすことができます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 大きな意味の目的は「経営改善の諸コンサルティング」です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 顧問契約サービスは経営に関すること、財務・会計に関すること、法律事項に関することなど、総合的な相談とアドバイスをするコンサルティング業務となります。したがって、基本的には年単位の契約方式をとり、月間訪問する頻度、主要テーマ、報酬等は協議・合意で決定することになります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 具体的な主要テーマの例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・資金繰り相談 ・売掛金の回収 ・買掛金の圧縮 ・社員とのトラブル相談 ・会社内での不祥事 ・顧客の整備と拡大策 ・月次決算 ・事業計画の策定 ・職場の風土改善 ・コンプライアンス ・社内の諸制度の整備(就業規則、賃金規定、評価システム、目標監理、教育体系など) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇ | 標準となる料金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
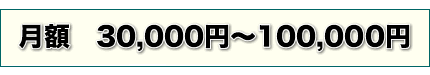 詳細はぜひお問い合わせください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M&A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | M&Aとは合併(Merger)と買収(Acquisition)のことです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 具体的には、株式の売却、買収、事業譲渡、事業の譲受け、合併、資本参加、株式交換等のことです。 新聞紙上で大手企業のM&Aが華々しく取り上げられますが、近年、後継者難を背景に第三者への事業承継の手段として、また、経営戦略の機動的展開手段として中堅・中小企業のM&Aも年々増加しております。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | M&Aは大企業の経営戦略だけではありません | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M&Aというと、大手企業のこととお考えかもしれませんが、実際には中堅・中小企業の会社の譲渡と会社の譲受けの実例は、確実に増加しております。M&Aが「後継者問題の解決」と「さらなる発展」を目指す中堅・中小企業の有力な経営戦略の一環になってきました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 後継者のいない企業のためのM&A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昨今は、子供が会社を継がないので、経営をきちんと継続してくれる会社に経営を譲渡したいという例が増えています。 無理に子供に会社を継がせず、子供には好きで、得意な道を歩ませた方が、会社や社員にとっても、本人にとっても幸せだと考えることが、浸透してきています。 会社が黒字で順調なときに、そして自分も元気なうちに、会社をより成長させてくれる可能性のある企業に経営を任せて、経営に節目をつけたいと考えるオーナー経営者が多く居られます。 中堅・中小企業のM&Aでは会社譲渡後もそのまま存続し、社員も全員そのまま継続雇用されるのが原則です。そして経営者は譲渡後すぐに引退するのではなく、会長・相談役等でしばらくの間業務の引き継ぎのために会社に残っていただき、円滑に次の経営者に経営をバトンタッチしていただいております。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 事業の将来性対応型M&A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境が、激変するなかで、どの事業も従来のやり方では生き残れません。 自らも変革しつつ他社の技術・ノウハウと結びつき、それを積極的に活用する攻めの経営に転換する企業が現れております。「第2、第3の創業」として経営の選択肢の一つとしてM&Aの活用がそれです。 このような、課題を解決できる可能性が高い経営戦略として、友好的M&Aがあり、多くの成功事例がそれを証明しております。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | M&Aのメリット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 用語解説 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | M&Aの流れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | M&Aの直近の事例(関東のみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒306-0126 茨城県古河市諸川1709-6
TEL 0280-76-4767 FAX 0280-76-4769